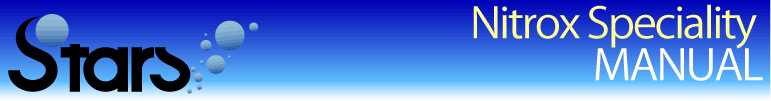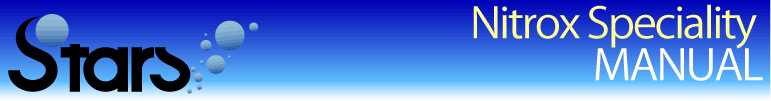■1日複数回潜水の潜水時間管理
最後の潜水から24時間を超える水面休息時間をとらずに2回目以降の潜水を行う場合には、最後の潜水により吸収した酸素が体内に蓄積されています。
2回目以降の潜水には、1回目の潜水後に体内に蓄積している酸素量を考慮しなければなりません。
それぞれのダイビングで潜水時間や潜水深度が異なることがあるので、酸素比率暴露表を利用して潜水前の酸素の吸収量を計算し、次の潜水の酸素暴露限界時間を求めます。
例えば、EAN36を使用して水深28mに30分潜水し、水面休息をとった後にEAN36を使用して水深28mへ第2回目の潜水をする場合の酸素暴露限界時間は何分でしょうか。
第1回目の潜水ではEAN36の酸素比率は0.36ですから、計算式を利用すると、
酸素分圧=0.36(28÷10+1)=1.386 となります。
表の左端の欄で1.386以上の最も近い数値を探します。
酸素分圧1.40が最も近い数値です。
その右の欄に5分間隔で記載されている酸素暴露時間で、35分※の欄に酸素暴露限界比率23%となっています。
このことは、酸素暴露限界時間まで、まだ77%の余裕があることを示しています。
※ 酸素暴露時間は、安全面を考慮して、それぞれ5分未満、10分未満、15分未満と考えます。
従って30分潜水した場合には、:30ぴったりの欄ではなく、次に大きい:35の欄を見ます。
|
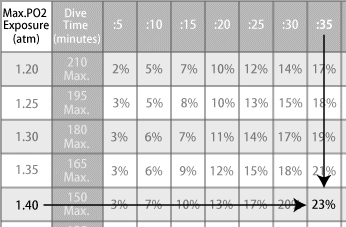 |
|
第2回目の潜水は第1回目の潜水と同様ですから、酸素分圧1.40の欄を右にたどり、酸素暴露限界比率の77%を探します。
この表には酸素暴露限界比率40%までしか記載がありませんから、酸素暴露限界比率40%の酸素暴露時間59分※が酸素暴露限界時間となります。
※ 酸素暴露時間は、安全面を考慮して、それぞれ5分未満、10分未満、15分未満と考えます。
従って「: 60」の酸素暴露時間は60分未満、すなわち59分となります。
|
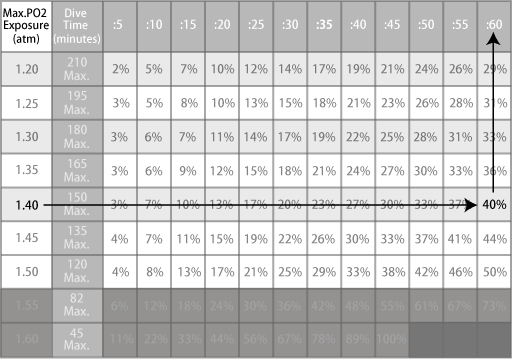 |
また、EAN36を使用して水深28mに30分潜水し、水面休息をとった後にEAN36を使用して水深28mへ30分潜水し、さらに水面休息をとった後にEAN36を使用して水深28mへ第3回目の潜水をする場合の酸素暴露限界時間は何分でしょうか。
第1回目の潜水ではEAN36の酸素比率は0.36ですから、計算式を利用すると、
酸素分圧=0.36(28÷10+1)=1.386 となります。
表の左端の欄で1.386以上の最も近い数値を探します。
酸素分圧1.40が最も近い数値です。
その右の欄に5分間隔で記載されている酸素暴露時間で35分の欄に酸素暴露限界比率23%となっています。
このことは、酸素暴露限界時間まで、まだ77%の余裕があることを示しています。
|
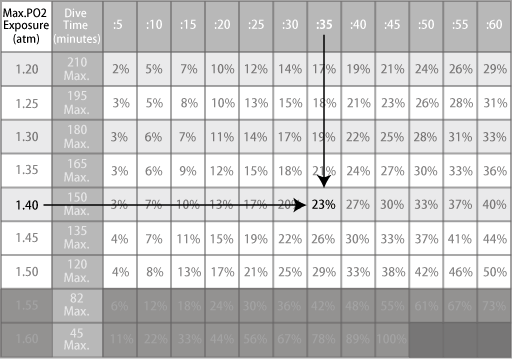 |
第2回目の潜水は第1回目の潜水と同様ですから、酸素暴露限界比率は23%となります。
第1回目の潜水終了後の酸素暴露限界比率と第2回目の潜水終了後の酸素暴露限界比率を合計して、第2回目の潜水が終了した時点での酸素暴露限界比率46%を求めます。
このことは、酸素暴露限界時間まで、まだ54%の余裕があることを示しています。
第3回目の潜水は第2回目の潜水と同様ですから、酸素分圧1.40の欄を右にたどり、酸素暴露限界比率の54%を探します。
この表には酸素暴露限界比率40%までしか記載がありませんから、酸素暴露限界比率40%の酸素暴露時間59分が酸素暴露限界時間となります。
|
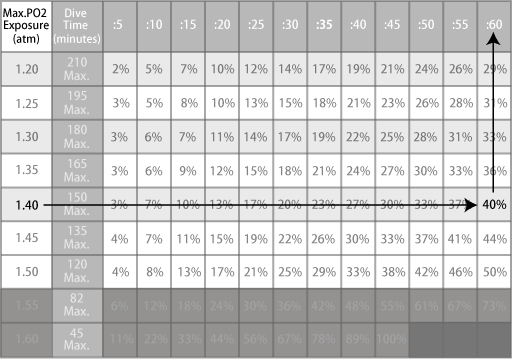
|
アメリカの専門機関では、酸素中毒のリスクを少なくするために、水面休息時間を90分以上にすることが望ましいとしています。 |
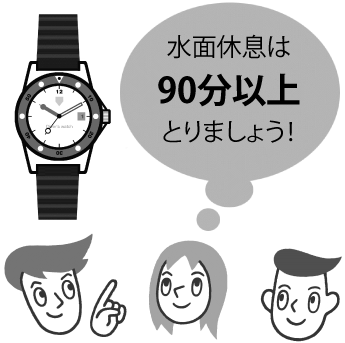 |